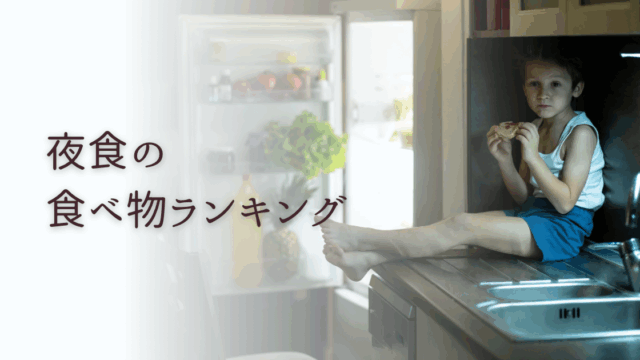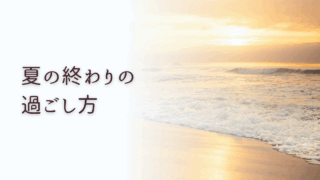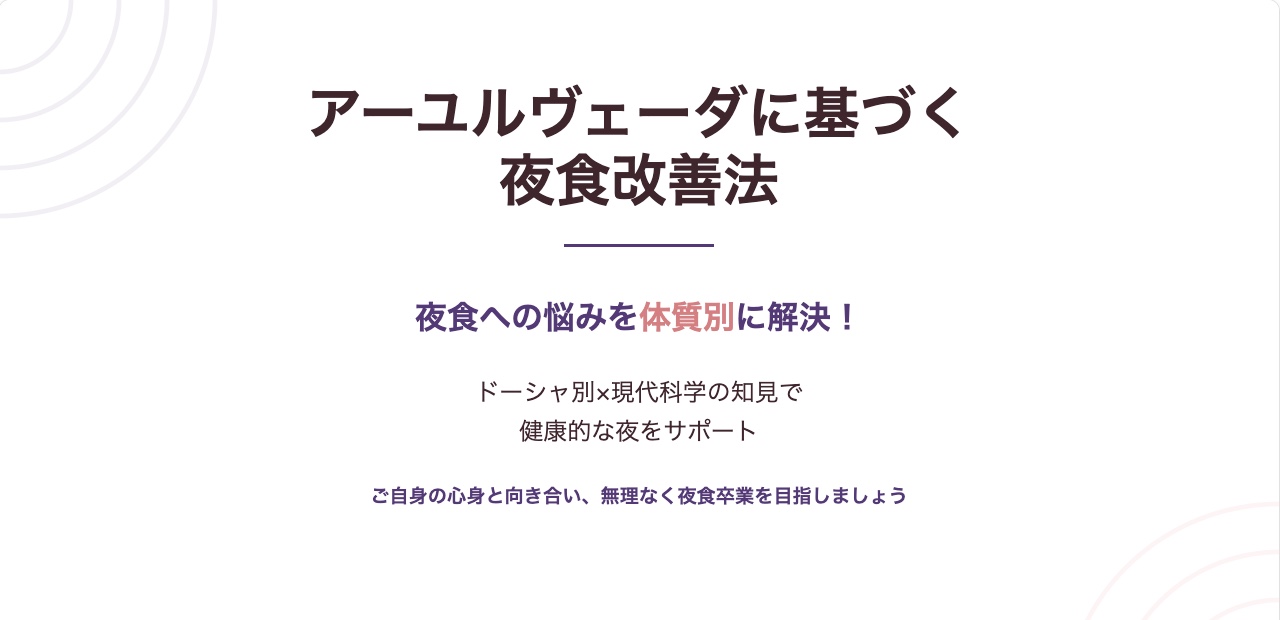
パッと読むためのもくじ
はじめに|「また夜に食べてしまった…」を卒業したい人へ
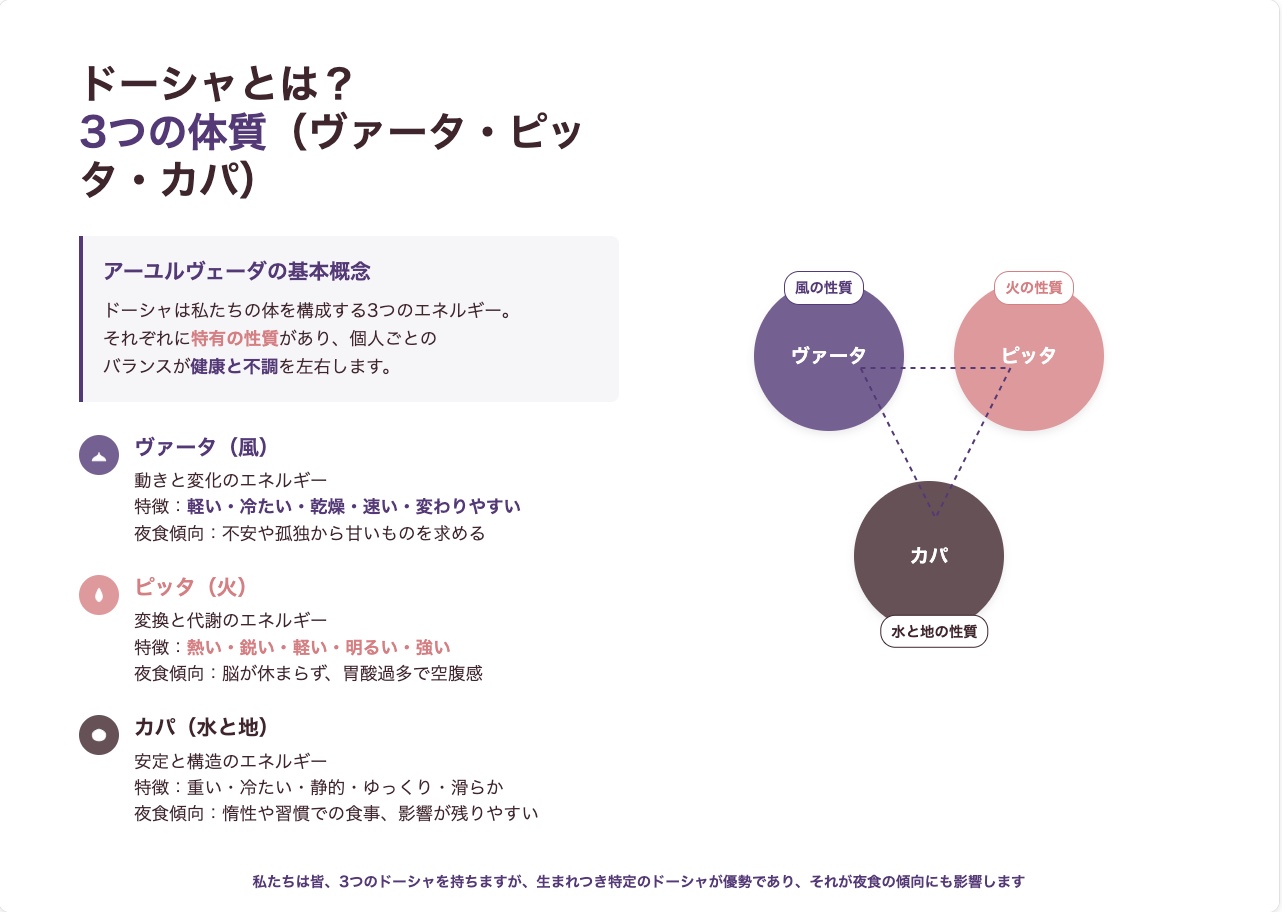 寝る前になると、つい何かを食べたくなる。
寝る前になると、つい何かを食べたくなる。
これは単なる“意志の弱さ”ではなく、体質(ドーシャ)の乱れや感情の影響で自然に起こる反応なのです。
アーユルヴェーダでは、私たちの体質を「ヴァータ・ピッタ・カパ」に分け、それぞれに食欲の現れ方、消化力、感情の動き方に傾向があると考えます。
この記事では、夜食がやめられない原因をドーシャ別に掘り下げ、やめるための実践的な方法と代替食、翌朝のリセット法まで丁寧に解説します。
アーユルヴェーダの基本|なぜ夜の食事は注意が必要?
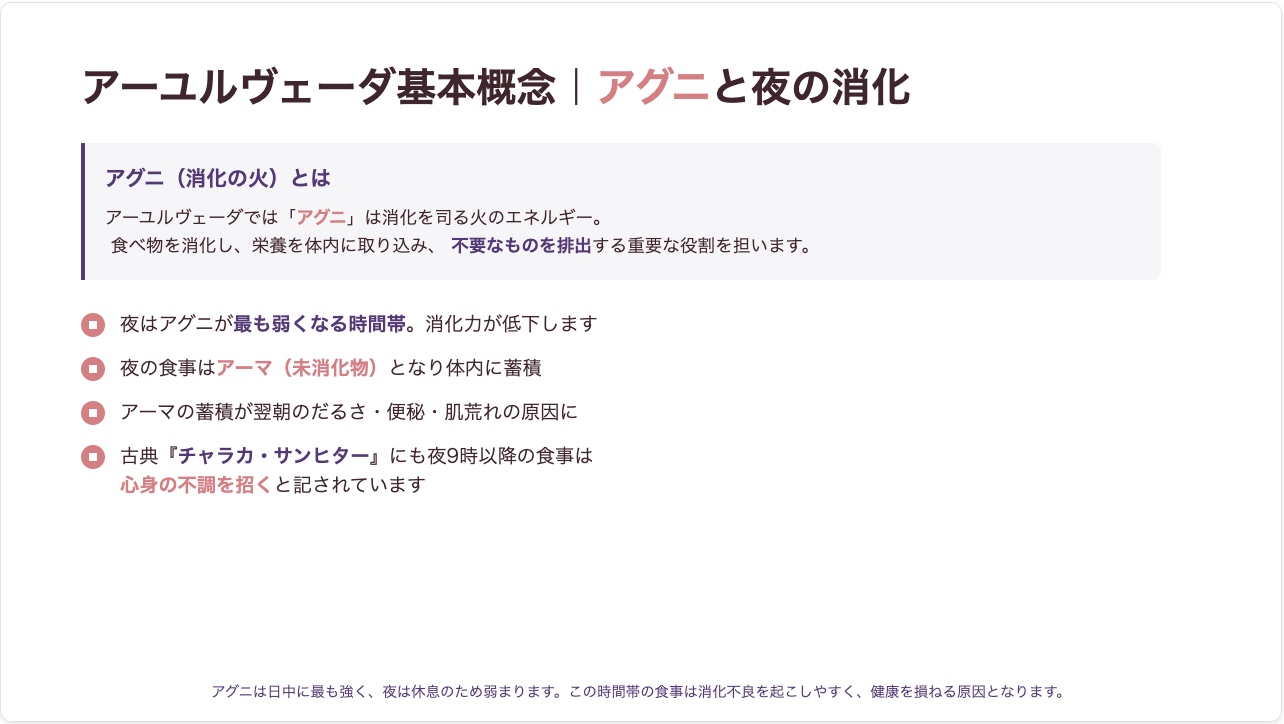 アーユルヴェーダでは「アグニ(消化の火)」を非常に重視します。
アーユルヴェーダでは「アグニ(消化の火)」を非常に重視します。
夜はアグニが最も弱くなる時間帯。この時間帯に食べたものはアーマ(未消化)になりやすく、以下の不調を招くとされます。
- 翌朝のだるさ・便秘・肌荒れ
- 睡眠の質の低下
- 代謝の乱れ・太りやすくなる
古典にも「夜9時以降の飲食は心身の不調を招く」と記されています(出典:Charaka Samhita)。
ドーシャ別|夜食したくなる原因と“やめるヒント”
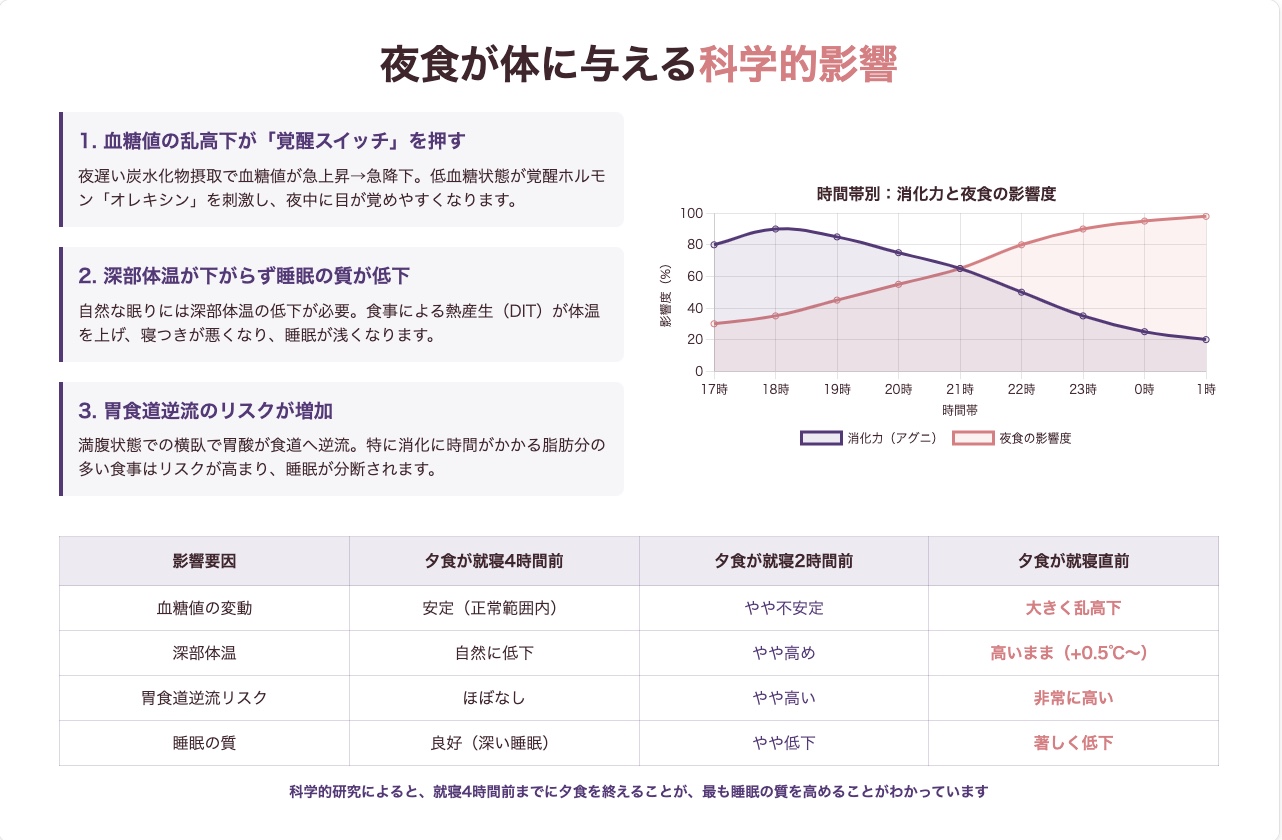
ヴァータ(Vata):不安・孤独で“食べて落ち着きたい”
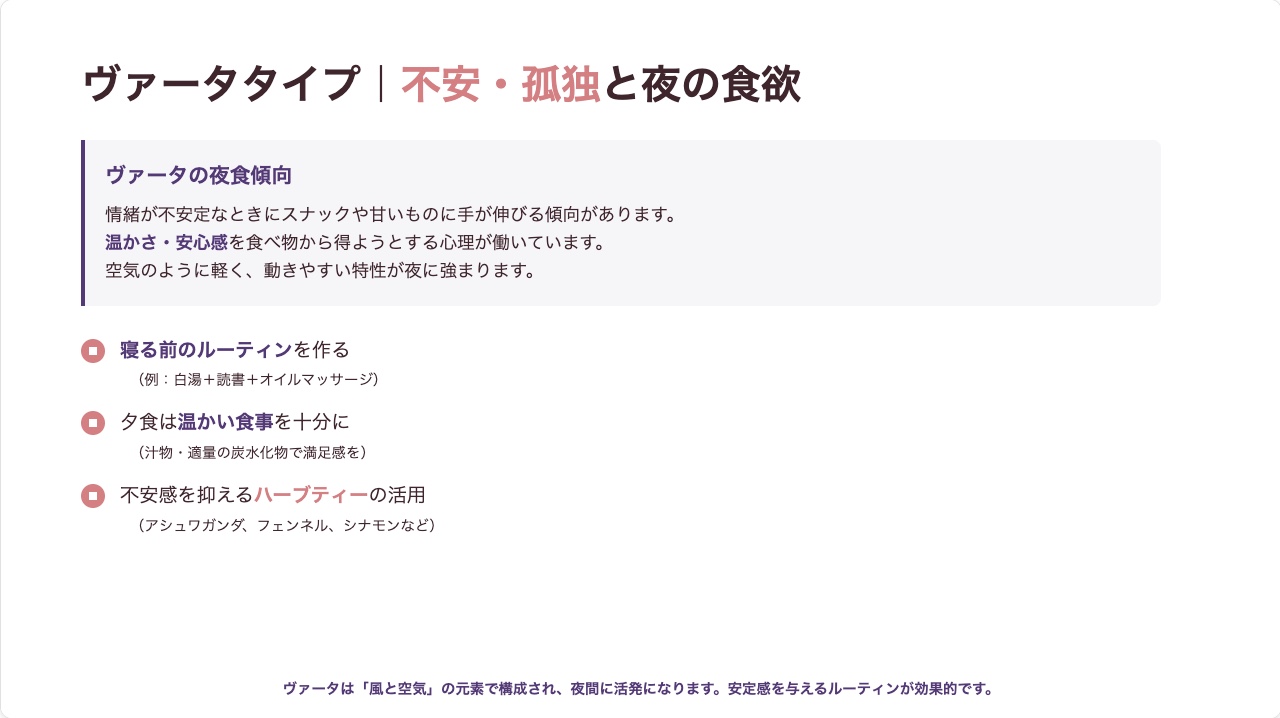
原因
情緒が不安定で、スナックや甘いものに手が伸びる傾向。温かさ・安心を食べ物で得ようとする。
やめ方のヒント
- 寝る前のルーティンを作る(例:白湯+読書+オイルマッサージ)
- 温かい食事を夕食で摂る(汁物・炭水化物)
- 不安感を抑えるハーブティー(アシュワガンダ、フェンネル)
ピッタ(Pitta):脳が“オフ”にならず活動が止まらない
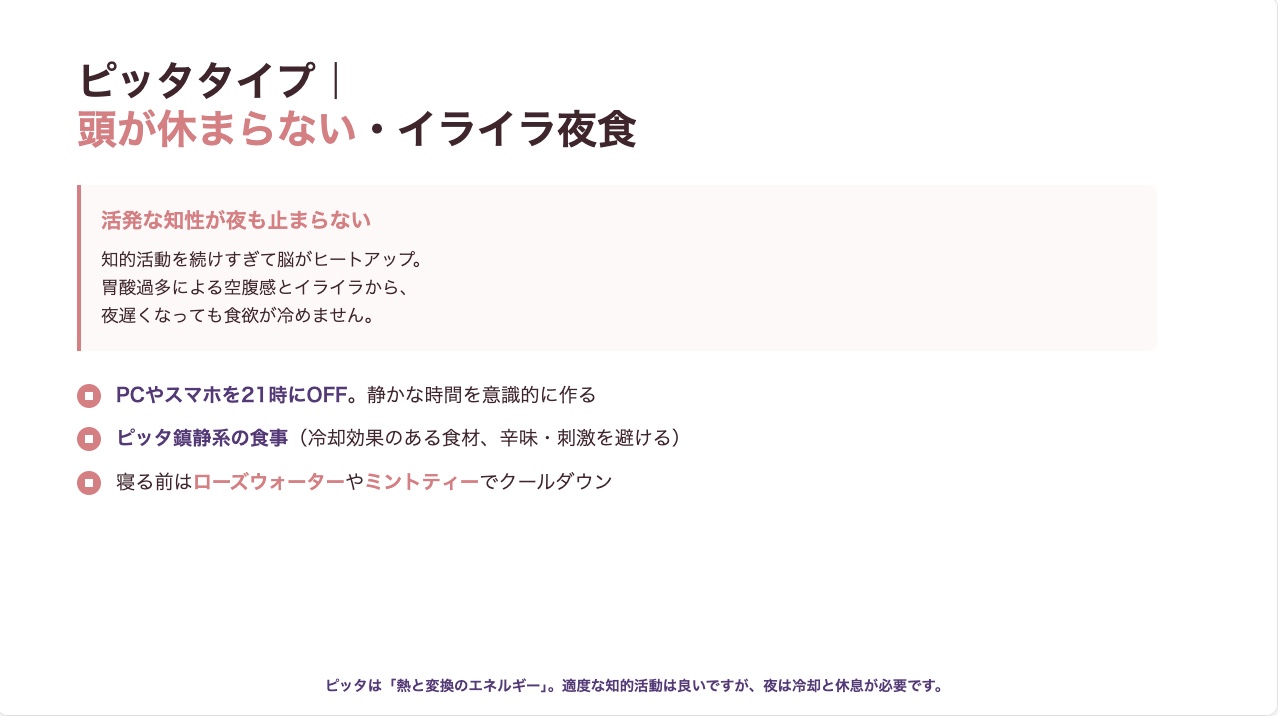
原因
知的活動を続けすぎて脳がヒートアップ。
胃酸過多による空腹感、イライラを伴うことも。
やめ方のヒント
- PCやスマホを21時にOFF。静かな時間を意識的に作る
- ピッタ鎮静系の食事(冷却効果のある食材、辛味・刺激を避ける)
- 寝る前はローズウォーターやミントティーでクールダウン
カパ(Kapha):なんとなくの“惰性食い”が多い
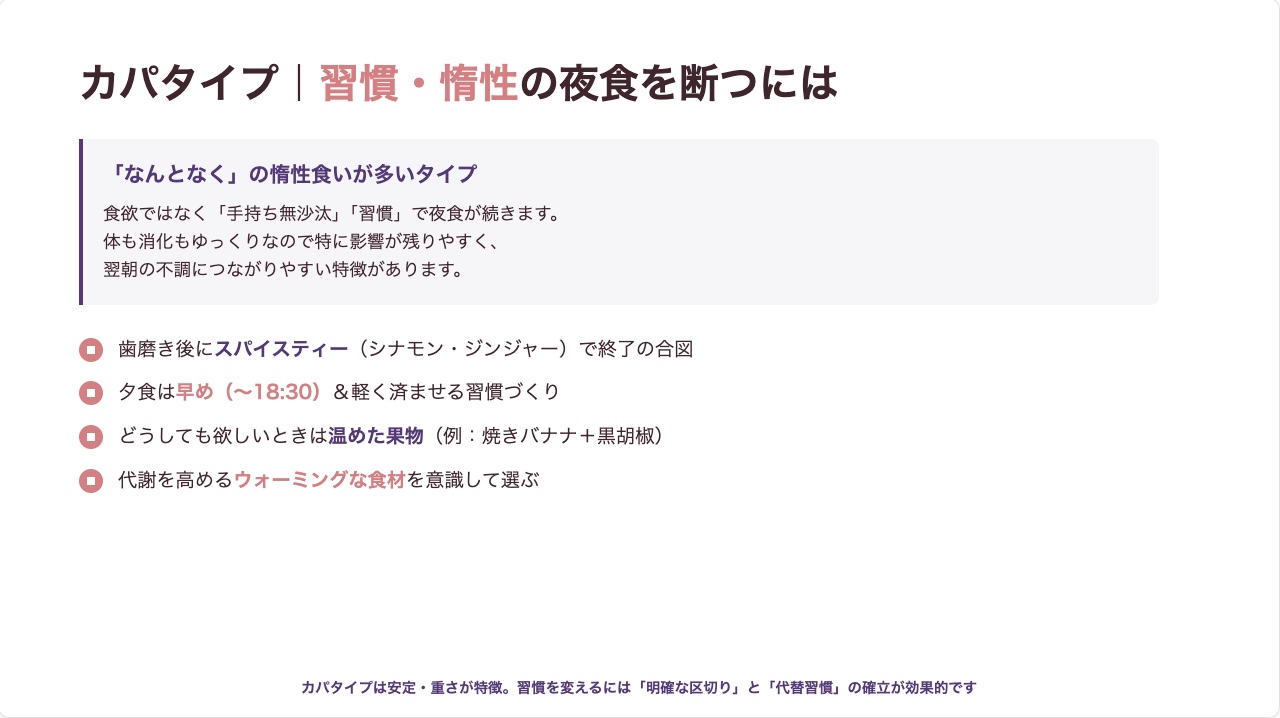
原因
食欲ではなく「手持ち無沙汰」「習慣」で夜食が続く。
体も消化もゆっくりなので特に影響が残りやすい。
やめ方のヒント
- 歯磨き後にスパイスティー(シナモン・ジンジャー)で終了の合図
- 夕食は早め(〜18:30)&軽く済ませる
- どうしても欲しいときは“温めた果物”(例:焼きバナナ+黒胡椒)
どうしてもお腹がすいたときの代替案(ドーシャ別)
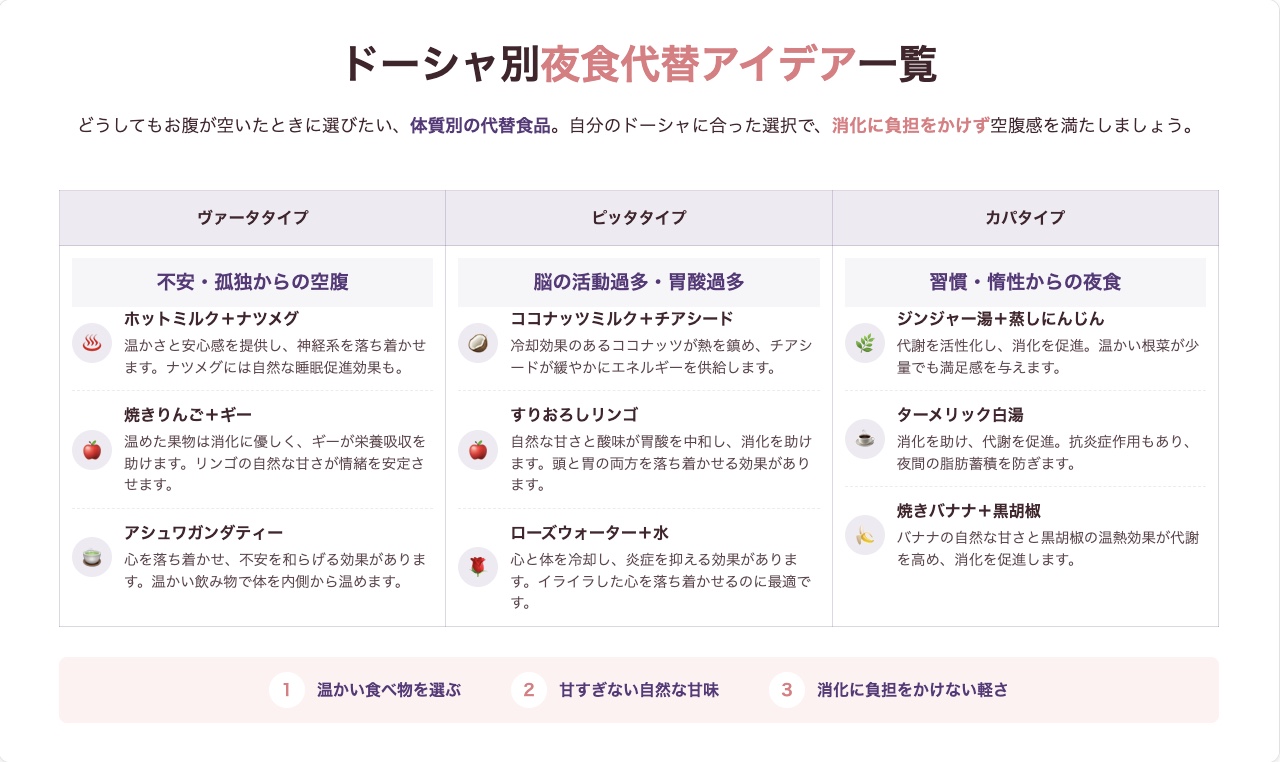
| ドーシャ | 代替アイデア |
|---|---|
| ヴァータ | ホットミルク+ナツメグ、焼きりんご+ギー |
| ピッタ | ココナッツミルク+チアシード、すりおろしリンゴ |
| カパ | ジンジャー湯+蒸しにんじん、ターメリック白湯 |
※すべて「温かく」「甘すぎず」「消化しやすい」ことがポイントです。
夜食してしまった翌朝のリセット習慣

- 起床後に白湯をゆっくり飲む(胃腸をリセット)
- 舌掃除でアーマチェック&排出
- 朝食は果物orキチュリ(軽くて消化が早いもの)
- 散歩や軽いストレッチで代謝を上げる
- 昼をメインに、夜を軽く(リズムの再構築)
まとめ:やめ方は“制限”ではなく、“体質理解”から
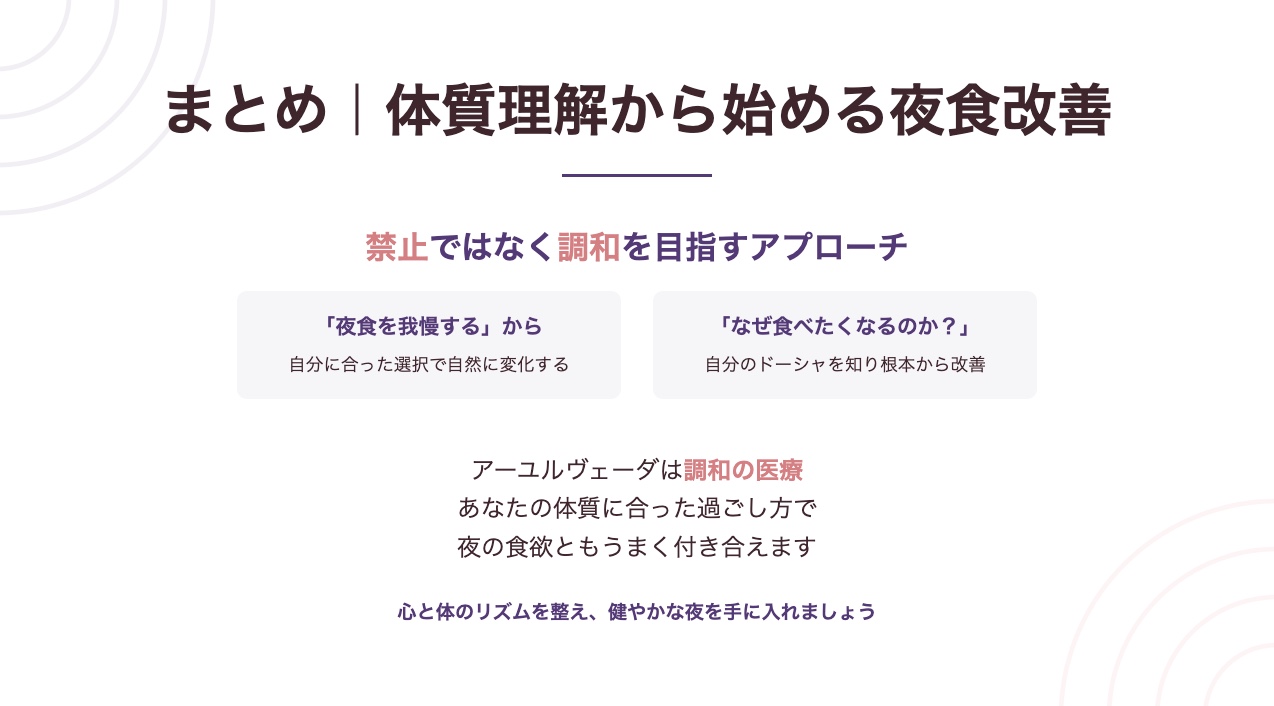
「夜食を我慢する」のではなく、「なぜ食べたくなるのか?」を知ることで、自分に合った自然な対策ができるようになります。
アーユルヴェーダは“禁止”ではなく、“調和”の医療。
あなたのドーシャに合った過ごし方を知れば、夜の食欲とうまく付き合っていけます。
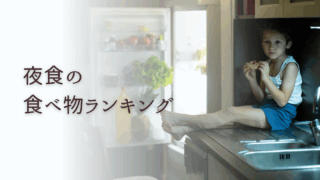


参考リンク
Sri Sri Ayurveda Hospital – Sleep and Diet
LifeSpa – Ayurvedic Night Eating Guide
NCBI – Chrononutrition and Late Eating