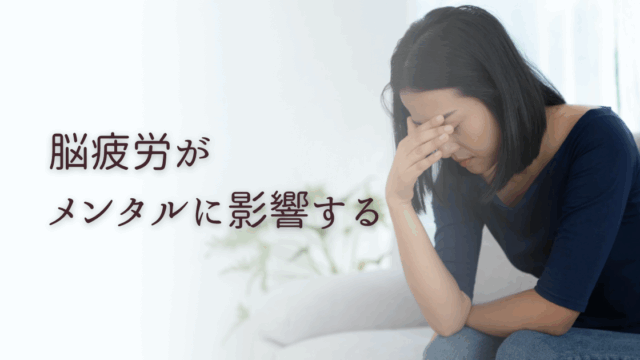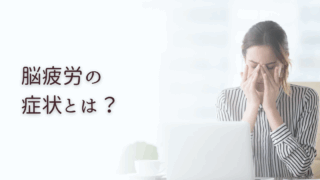パッと読むためのもくじ
はじめに
アーユルヴェーダでは「スネハ(油)」が心身の潤いとバランスを保つ重要な役割を担います。
市販品も便利ですが、自分の体質や目的に合わせて手作りオイルを使うことで、セルフケアの深みが変わります。
本記事では、オイルそのものの意味から、体質別の素材選び、手作り方法、そして使用法までを総合的にご紹介します。
アーユルヴェーダにおけるオイルの役割
オイルは「愛情」を象徴するとされ、アビヤンガ(体全体のマッサージ)やナスヤ(鼻うがい)、プリグなどによって心身に栄養と安定を届けます。
不安定なヴァータを鎮静化し、乾燥や冷えを和らげる基本療法として欠かせません。
オイルの種類①:ベースオイル(キャリアオイル)
アーユルヴェーダでよく使われる基本オイルには以下があります。
- セサミオイル(ごま油):万能オイル。ヴァータを整え、温めと保護効果が高い。キュアリングで純度が高まり吸収率も向上。
- ギー(澄ましバター):浄化と解毒を担う“奇跡のオイル”。火と風の性質を調整し、記憶力や免疫にも貢献。
- ココナッツオイル:冷却・炎症鎮静に優れ、熱を帯びたピッタ体質に適します。
- ひまし油(キャスターオイル):関節痛や腸の不調に効く、デトックス的な特質があります。
- マスタードオイル:カパ体質や寒冷時に適した、ピリッと温める力を持つオイル。消化促進や血流改善にも寄与します。
- オリーブ/アーモンド/ホホバなどの植物性キャリアオイル:補助として、軽い使い心地や肌馴染みを求める際に活用可能です。
オイルの種類②:ハーバルオイル(薬草配合オイル)
ベースオイルにハーブを煮出したハーバルオイルは、特有の治癒力を持ちます。
代表例を紹介します。
- アシュワガンダ・タイラ:深いリラックスと睡眠促進。神経系を鎮める効果があります。
- クシーラバラー・タイラ:女性ホルモンバランスや更年期に◎。
- クマーリ・タイラ:冷却効果があり、ピッタの熱を落とす。頭部ケアにも。
- クンクマーディ・タイラ:サフランエキス入りフェイシャルオイル。美白・肌再生に。
- シッダールタ・タイラ:冷え・筋肉痛・ヴァータ・カパ両方の調整。
- トリファラー・タイラ:3ドーシャバランス調整・デトックス・老化防止。
スピリチュアルな目的では、ストゥパ点灯に用いられるオイルもあり、セサミ・ギー・マスタード・ココナッツそれぞれが精神性や祝福を象徴します。
オイル作りの基本手順
以下はシンプルなハーバルオイルの作り方です。
- ベースオイルと乾燥ハーブを鍋に入れ、弱火で1時間ほど煮る。
- 色と香り、泡の状態を見て火を消し、常温に冷ます。
- 布で濾し、遮光瓶に保存。冷暗所で保管し、1ヶ月程度が目安。
セサミオイルは「キュアリング」(90℃加熱後自然冷却)が品質向上に有効です。
ギー作りは、無塩バターを弱火で煮て水分と不純物を除く澄まし操作で完成します。
目的別おすすめオイルレシピ
脳の疲れ・ストレスケア
セサミオイル+アシュワガンダ→ヘッドマッサージで神経を鎮める。
美肌・エイジングケア
ギー+サフラン・ローズウォーター→軽く顔パッティング。
冷え・血行改善
マスタードオイル+ターメリック→温かい脚マッサージに。
使用上の注意事項
- 初回はパッチテストをしてアレルギー反応の確認を。
- 妊娠中や持病がある場合は専門家に相談しましょう。
- 加熱直後のオイルは熱すぎるため、温度確認を。
- ギーは脂質が多いため摂取は控えめに(1日小さじ1が目安)。
まとめ
アーユルヴェーダのオイルケアは、ただの癒しではなく、体質と目的に合わせて調整する“パーソナルセラピー”です。
基本のベースオイルから薬草のチョイス、手作りプロセス、使用シーンまで、すべてが自分らしい調和への道しるべ。
まずは一種類から作り、手間と効果の喜びを感じてください。