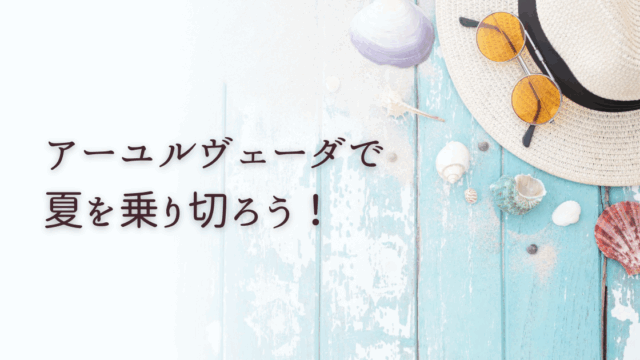パッと読むためのもくじ
はじめに:なぜ私たちは食べ過ぎてしまうのか?
「お腹がいっぱいなのに、手が止まらない」
「イライラや寂しさで食べてしまう」
「健康のためと思って食べたのに、体が重だるい」
そんな“食べ過ぎ”の経験、誰にでもあるのではないでしょうか。
アーユルヴェーダでは、食べ過ぎはアグニ(消化の火)を弱め、アーマ(未消化物)を生み出すとされています。
そしてその背景には、「体質=ドーシャの乱れ」「感情と食のズレ」「消化力の低下」といった根本原因があるのです。
この記事では、アーユルヴェーダの視点で食べ過ぎのメカニズムを解説し、ヴァータ・ピッタ・カパ体質別の原因とリセット法、そして“食べ過ぎない”ための日常ケアまで具体的にご紹介します。
食べ過ぎのアーユルヴェーダ的な見方
アーユルヴェーダでは、私たちの体の中には消化の火「アグニ」があるとされ、健康の維持にはこのアグニのバランスがとても重要です。
食べ過ぎがアグニを乱すメカニズム
- 必要以上に食べる → 消化酵素が追いつかない
- 消化しきれない → アーマ(毒素)が発生
- アーマが蓄積 → 代謝の乱れ、不調、慢性的な疲れ・肥満へ
ドーシャ別|食べ過ぎの傾向とその理由
ヴァータ(Vata)タイプ:空腹と不安を混同しやすい
特徴
軽く乾いた体質。
神経が繊細で感情の波が激しい。
食べ過ぎのパターン
- 緊張・不安で“ちょこちょこ食べ”
- 早食い・空腹感の錯覚
- 夜遅くになってから食べ出す
心理的背景
安心したい、気を紛らわせたいという衝動。
ピッタ(Pitta)タイプ:燃焼系で“腹が減って怒る”
特徴
消化が強く、食べ物がすぐ燃えてしまう。
食べ過ぎのパターン
- 食事を抜いた反動でドカ食い
- 辛い・揚げ物・肉を好む
- 外での刺激に反応して食欲増進
心理的背景
パフォーマンス重視、自己制御を緩めにくい。
カパ(Kapha)タイプ:習慣と情緒から“つい食べ”
特徴
体格がしっかりしていて代謝がゆるやか。
食べ過ぎのパターン
- 習慣的に間食・夜食
- 甘いものへの依存
- 食べた後でも「もっと食べたい」感覚
心理的背景
退屈や感情を食で埋めがち
食べ過ぎたときの体質別リセット法
共通:消化火を立て直す“白湯断食”
- 朝は白湯だけで過ごす(400〜500mlを分けて)
- 舌苔チェック(白い苔=Amaサイン)→ 舌掃除
- お腹が空いたら、次の食事は軽く温かく、スパイス入り
ヴァータ向けリセット法
- キチュリ(ムング豆+米)にギーを少量加える
- 生姜入りの白湯 or フェンネルティーを少量ずつ飲む
- 夜はナツメグ入りのホットミルクで神経を休める
ピッタ向けリセット法
- アロエジュースやミント水で熱を鎮静
- キチュリにターメリック+コリアンダー+クミンで調整
- スマホ断ち+読書や自然音で内側をクールに
カパ向けリセット法
- 朝イチで軽めの運動(ウォーキングor太陽礼拝)
- 朝食は抜き or 温めた果物(焼きリンゴ・蒸しにんじん)
- スパイス白湯(ジンジャー・ブラックペッパー・シナモン)
習慣化で食べ過ぎを防ぐ「日常の整え方」
① 食事は“8分目”で止める
「アグニが働ける余白を残す」=空腹感と満足感のちょうど中間がベスト。
② 食事時間を整える(ディナチャリア)
- 朝食:軽め(7〜8時)
- 昼食:1日の主食(12時前後)
- 夕食:軽くて温かく(18〜19時)
※特にカパ体質は「朝断食+昼しっかり」が◎
③ 食事中は“静かに集中”
- TV・スマホを消す(ながら食べNG)
- よく噛む(30回以上)
- 感謝して食べる(マインドフルイーティング)
食べ過ぎないための“簡単スパイスレシピ”3選
ジンジャーレモン白湯(全体質対応)
白湯200ml+生姜スライス1〜2枚+レモン汁数滴
→ 食前に飲むことで食欲を整える
アグニ活性ペースト(ヴァータ・カパ向け)
生姜すりおろし小さじ1+レモン汁小さじ1+塩少々
→ 食事の10分前に少量摂取でAgni点火
スパイスキチュリ(全体質対応)
米+ムングダル+ギー+クミン+コリアンダー+ヒング+ターメリック
→ 消化に優れ、心も整う万能食
まとめ:体質に合った“付き合い方”で、食欲は整う
食べ過ぎをやめたいなら、まずは“自分の体質と感情のクセ”に気づくことが第一歩です。
アーユルヴェーダは制限を押しつけるのではなく、「食べたい気持ちとどう付き合うか」を教えてくれる医学。
食べ過ぎたら、リセットすればいい。
そして、日常の中に少しずつ整える習慣を取り入れていけば、自然と“必要なものを、必要な量だけ”選べるようになっていきます。
関連記事リンク
参考文献・信頼リンク
上馬場和夫・西川眞知子『新版インドの生命科学 アーユルヴェーダ』(農文協)
LifeSpa – Agni and Overeating
Art of Living – Mindful Eating
NCBI – Eating Behavior and Circadian Rhythms