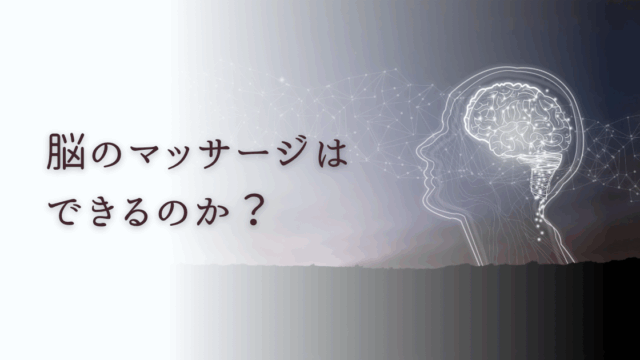アーユルヴェーダでは、季節ごとのドーシャ性質を理解し、それに合わせた生活習慣を整える「リトゥチャリヤ(季節の養生法)」を提唱します。
春はカパ優勢、夏はピッタ優勢、秋から冬にかけてはヴァータが高まりやすいため、それぞれに対応した食事・生活リズム・セルフケアが重要です。
本記事では、6つの季節それぞれに適した具体的な過ごし方・飲食・習慣・注意点をわかりやすく解説します。
パッと読むためのもくじ
春(ヴァサンタ:3月中旬〜5月中旬)
春は冬に蓄積されたカパ(湿・重)が溶け出して増加する季節。
花粉症・むくみ・だるさ・眠気などが起こりやすく、呼吸器症状も出やすくなります。
- 食事:消化のよい苦味・渋味・辛味を控えめに取り入れて、軽く温かい食材を中心に。春野菜や新芽・苦味の野菜が効果的
- 生活習慣:朝日を浴びて起床。午後の昼寝は避ける。温オイルマッサージ(アビヤンガ)やスチームで巡りを促進
- 体調管理:鼻うがい、花粉対策、適度な運動でカパの停滞を防止
夏(グリシュマ:5月中旬〜7月中旬)
夏はピッタ(火性)が高まる季節で、炎症・暑さ・消化力低下・イライラなどが出やすくなります。
- 食事:軽く冷たい性質のある食材(キューリ、水やワカメ類、バターミルク)を中心に、辛味の強いものや酸味、発酵物は控えるのが望ましい
- 生活:涼しい場所で日陰を選び、白檀やミントペースト、薄着などで体温調整。昼寝や過度な運動を避ける
- セルフケア:ラベンダーなど冷却アロマ、ヨガや軽い瞑想で内熱調整
モンスーン(ヴァルシャ:7月中旬〜9月中旬)
モンスーン期は湿度と冷えが増し、ヴァータとピッタが影響を受けて体調不安定になりがち。
消化力の低下、疲れやすさ、気分の揺れなどが特徴です。
- 食事:温かく調理した食材を中心に、軽めで温性のもの。消化を助けるスパイスを少量使用
- 生活:冷え対策として湯浴みや温かい飲み物、オイルマッサージで巡りを促します
- セルフケア:日々の観察を重視し、体調に応じた柔軟な調整を実践
秋(シャラダ:9月中旬〜11月中旬)
秋はヴァータが増加する時期で、風や乾燥の影響を受けやすくなります。
骨・関節のこわばり、眠りの浅さ、神経過敏などが起こりやすくなります。
- 食事:温かくて油分のある根菜や煮込み料理がおすすめ。甘味・塩味を適度にとり、乾燥性の食材を避ける
- 生活:夜は早く寝て昼寝を避け、身体を温める衣服やルーム環境を整える
- セルフケア:セサミオイルで自己マッサージ(アビヤンガ)、ストレッチやヨガで関節をゆるめる。
初冬・厳冬(ヘマント/シシラ:11月中旬〜3月初旬)
冬期はカパが再び蓄積されやすく、冷気によりヴァータが活性化します。
消化力の鈍化・冷え性・代謝の低下・免疫力低下などに注意が必要です。
- 食事:温性・重性のある調理された食事(スープ、煮込み、乳製品)を中心にする。生野菜や冷たい飲料は控える
- 生活:暖かい衣服・湯浴み・暖色照明で身体を保温
- セルフケア:温オイルマッサージ前に温めた環境でアーユルヴェーダオイルを用いた自己ケア
全季節に共通する生活習慣
- 日の出前の起床(ブラフマムフールタ)を目指す
- 朝の舌掃除・オイルうがい・白湯の習慣
- 季節に応じた食事5味(甘・塩・酸・苦・渋・辛)をバランス良く取り入れる
まとめ
- アーユルヴェーダのリトゥチャリヤは、季節ごとのドーシャの変化を理解し、心身のバランスを整える最適な方法。
- 春はカパ、夏はピッタ、秋・冬はヴァータを意識して過ごすことで、不調を予防し快適な毎日を保てます。
- 日常には、食事・ルーティン・セルフケアを小さな習慣として取り入れ、心と体を調和させましょう。